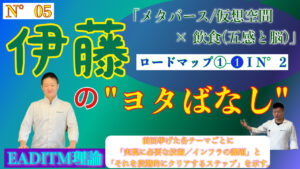
ロードマップを一つずつ。ser.
------------
今回は、番外編。
------------
前回の
2-②:精神的な満足感を通じた健康維持
考察と参考文献候補:
「食べた気になる」体験が
幸福感や食欲抑制に及ぼす効果については、
**感覚特異的満腹感(Sensory Specific Satiety)**の概念や
フード・プレゼンテーションが
食事の満足感に与える影響に関する研究。
------------
から、この時に参考資料として上げた
参考文献について。①〜③。
------------
参考文献①
ロールズ博士の2006年の論文「The role of sensory properties in the regulation of food intake」は、
食物の感覚特性が摂食行動にどのように影響するかを探求しています。
彼女の研究では、食物の味、匂い、食感などの感覚特性が、
食事の満足度や摂取量に直接的な影響を与えることが示されています。
特に、同じ食物を繰り返し食べるとその食物の快楽度が低下し(感覚特異的満腹感)、
これが摂取量の減少につながることが明らかになりました。
一方で、食物の感覚特性に変化を加えることで、摂取量が増加する可能性も示唆されています。
この研究の結論として、食物の感覚特性は摂食行動の調節において重要な役割を果たしており、
食事の多様性や新規性が食欲や摂取量に影響を与えることが示されています。
これらの知見は、食事の設計や食欲のコントロール、さらには肥満の予防や治療においても重要な示唆を提供している。
------------
参考文献②
McCrickerd & Forde(2016)の論文
**「Sensory influences on the consumption of food and beverages: Moving beyond palatability」**は、
食品や飲料の摂取量に影響を与える感覚的要因について、単なる「美味しさ(palatability)」を超えて探ることを目的としています。
主なポイント
⑴美味しさだけでは摂取量を説明できない
:一般に「美味しい」と感じると食事量が増えると
考えられがちだが、それだけが要因ではない。
:例えば、食感、温度、香り、色なども摂取量に影響を与える。
⑵食品の質感(Texture)と満腹感の関係
:食品の硬さや粘度(例えば、スムージー vs. 固形食)が食事のペースや満腹感に影響を与え、結果として摂取量を変える。
⑶期待と知覚の相互作用
:人は食品に対する期待を持っており、実際の味や食感が期待と一致するかどうかが満足度や食事量に影響する。
:例えば、「濃厚なスープ」として提供されたものが実際には薄かった場合、満足感が低下し摂取量が増える可能性がある。
結論
:食品の感覚的要因(味・食感・温度・視覚的特徴など)は、食事の摂取量や満足感に大きく影響する。
:「美味しさ」だけが摂取量の決定要因ではなく、食事の構造や期待とのギャップも重要な役割を果たす。
:食品設計や栄養学的アプローチにおいて、感覚特性を考慮することが、健康的な食事選択や満腹感のコントロールに有効である。
この論文は、食品業界や栄養学において「感覚特性」を活用した摂食行動の調整が可能であることを示唆している点が重要。
------------
参考文献③
Wansink(2004)の論文
「Environmental factors that increase the food intake and consumption volume of unknowing consumers」 は、
人々が無意識のうちに食品を過剰摂取してしまう環境要因について調査したものです。
主なポイント
⑴食環境(Environmental cues)が摂取量を左右する
:食器の大きさ(大きな皿やボウルを使うと、気づかずに多く食べてしまう)。
:食べ物の視認性(目の前にある食べ物ほど摂取量が増える)。
:簡単に手が届くかどうか(距離が近いほど摂取量が増える)。
⑵ポーションサイズ(Portion size)の影響
:提供される量が多いほど、人は無意識に多く食べてしまう(例:「ラージサイズ効果」)。
:飲食店や食品メーカーのポーションサイズ拡大が、過食につながる可能性がある。
⑶社会的・心理的要因
:食事のペースは周囲に影響される(友人や家族と一緒に食べると、無意識に摂取量が増えることがある)。
:食事中の注意の分散(テレビを見ながら食べると、摂取量が増える)。
結論
:人は食べる量を自覚してコントロールしているわけではなく、環境要因によって無意識に影響を受ける。
:ポーションサイズや食器の大きさ、食べ物の見えやすさ、食事環境などを調整することで、過食を防ぐことが可能。
:肥満や過食問題の対策には、意識改革だけでなく、食環境を適切にデザインすることが重要。
この研究は、「なぜ人は気づかずに食べ過ぎるのか?」という問いに対し、環境要因の影響を強調した点が特徴的。
------------
#伊藤慎吾 #仮想空間 #メタバース
#料理人 #公邸料理人 #飲食 #メタ
#ムーンショット目標 #ネット時代の
#テクノロジー #AI
#メタバース飲食理論 #EADITM
Eating and drinking in the Metaverse
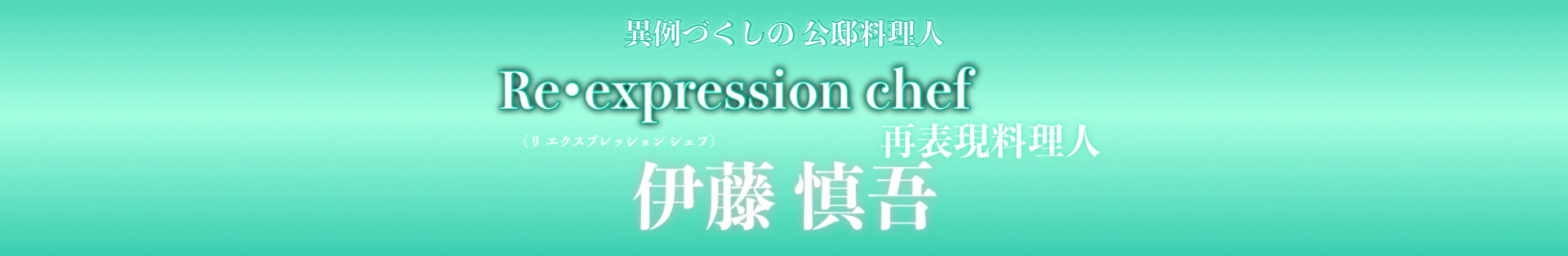
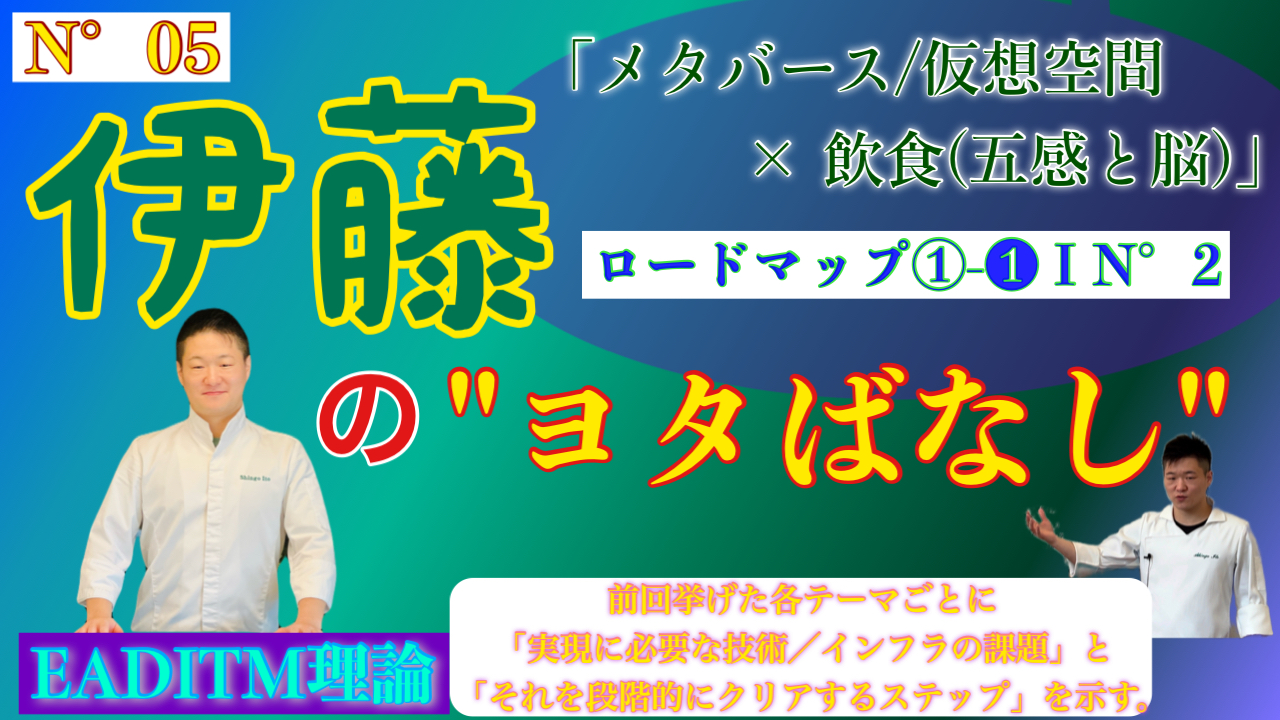


コメント