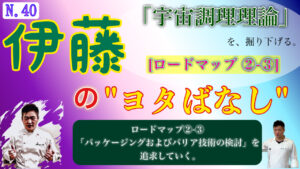
ロードマップを一つずつ。ser.
------------
「②-⑥殺菌・無菌化手法の確立」
------
それでは、同じく新章のロードマップ
「2. 食品の保存技術の確立:
– 長期保存可能で軽量・コンパクトな食品の開発や保存技術の研究を行う。」から
ロードマップ②-⑥として
殺菌・無菌化手法の確立
「高圧処理(HPP)、放射線照射、パルス電場(PEF)など、栄養を損なわずに微生物を確実に不活化する技術を選定し、最適化プロトコルを策定する。」
について追求していきたいと思います。
------------------
新章ロードマップ② 「食品の保存技術の確立:
– 長期保存可能で軽量・コンパクトな食品の開発や保存技術の研究を行う。」は、全体を通して
最終的に得られた知見をベースに「ISO規格」「Artemis協定」レベルの保存食品仕様を策定し、量産および国際共同利用に向けた設計を確定できる様にするのが一つのゴールとして進めていきたいと思います。— 「殺菌・無菌化手法」を宇宙(月面基地)向けに
実用的かつ論文化できるレベルで整理します。
以下はまず概観 → 各技術の評価(原理・代表的パラメータ・利点欠点)→ 月面での実装方針(推奨プロトコル例)→ 試験・検証ロードマップ、という順でまとめます。
重要な根拠には最近のレビュー/報告書を添えてあります(本文内に出典を示します)。
※「既出考察済み」な点(例:真空回収やフリーズドライの配置、エネルギー制約の重要性等)はここでは詳細は省略し、殺菌技術に特化して深掘りします。
------------------
概観(目的と制約)
月面基地での殺菌・無菌化は次を満たさなければなりません:
・確実な微生物不活化(食品安全)、
・栄養/官能(味・食感)へのダメージ最小化、
・装置の質量・エネルギー消費・可搬性の現実性、
・化学残留や作業者・環境への安全性(放射線等)、
・自動化・低メンテナンス性。
これらを天秤にかけつつ、単独技術より**ハードル技術(複数手法の組合せ)**で実運用とリスク低減を図るのが現実的です。NASAも長期ミッションに向けて微生物管理技術を多面的に検討しています。
------------------
各技術の要点評価(原理・代表パラメータ・利点/欠点)
以下、主要候補を列挙し、月面実用性の観点でコメントします。
1) 高圧処理(HPP:High Pressure Processing)
原理:等方的に高静水圧(通常 400–600 MPa)を短時間(数分)かけて微生物の細胞構造を破壊/不活化する非熱処理。
代表パラメータ:圧力 300–600 MPa、処理時間 1–10 分(食品種により異なる)。
利点:熱ダメージが小さく、食感・栄養の保持に優れる。密封パックのまま処理できる(後工程で無菌封入が可能)。
欠点(特に月面で):圧力容器が非常に重く、厚肉壁が必要 → 打上げコストと設置が大きな障壁。高圧ポンプや補機も重量・保守性の問題。大規模導入は現地製造(レゴリス資材)等の技術がないと難しい。
月面での適用提案:小容量のHPPユニット(パイロット)を検討可。ただし「打ち上げ質量」と「整備負担」を厳密評価要。
------------------
2) 食品照射(電子線/γ線/X線)
原理:高エネルギー放射線が微生物のDNAや細胞成分を損傷し不活化する。用途によりγ線(Co-60等)、電子線(E-beam)、X線がある。
代表パラメータ:微生物減少目的だと一般に数 kGy(例:肉類で 2–4 kGy、特定用途は 1–10 kGy/Codex上限や用途別基準あり)。
利点:有効で深達性がある(包装された状態でも照射可能)。設備は連続処理にも対応(e-beamは瞬間処理が可能)。
欠点(特に月面で):放射線源の安全管理・遮蔽(重い)・法規制が厳しい。Co-60のような放射性同位体を運搬・保管するリスクや国際的許可が必要。E-beamは「放射性物質を持たない」利点があるが、高電力で加速器設備が必要で、放射線散乱や遮蔽は不可避。
月面での適用提案:短期的にはe-beam(電子線)が現実性が高い(放射性物質無し)だが、遮蔽設計と放射線安全手順は必須。Codex等の国際基準に従う必要あり。
------------------
3) パルス電場(PEF:Pulsed Electric Field)
原理:液体や半液体製品に高電界(通常 15–50 kV/cm 範囲)を短パルス(µs–ms)で印加し、微生物の膜に孔(電穿孔)を作って不活化する。非熱的または低加熱での処理が可能。
代表パラメータ:電界強度 15–50 kV/cm、エネルギー投入 50–700 kJ/kg、パルス数や幅は食品物性に依存。
利点:液体食品(ジュース、スープ、ピュレなど)に非常に有効。比較的小型の装置で済む。熱変性が少ない。
欠点(特に月面で):固形物や大きな塊には適用困難。電気・高電圧設備の安全管理が必要。湿性の高い媒体の導電特性に依存。
月面での適用提案:液体系の再構成食品や野菜ピュレ等に優先導入。小型でバッチ対応可能なPEFユニットは「運搬性」と「コスト」の面で魅力的。
------------------
4) コールドプラズマ(低温プラズマ):表面殺菌
原理:大気・低圧ガスを電気的にイオン化し、活性種(ROS、RNS等)で微生物表面を破壊。加熱が少なく、包装外表面や果菜類表面に適する。
代表パラメータ:放電方式(大気圧プラズマ、低圧プラズマ)、処理時間数十秒〜数分、電力は装置により大幅差。
利点:低温で表面除染が可能。パッケージ表面や生鮮の表面汚染低減に極めて有効。装置は比較的コンパクト化が進んでいる。
欠点:深部(内部)まで作用しないため、内部汚染がある食品には不適。処理条件により酸化的影響が生じる可能性(風味変化)。
月面での適用提案:生鮮の表面処理(収穫直後)、パッケージ表面滅菌、器具の表面殺菌に最適。低消耗で運用負荷が小さい点が魅力。
------------------
5) UV-C(254 nm)/パルス光(PL)
原理:紫外線照射が微生物DNAを損傷して不活化。パルス光は高強度広帯域短パルスで同等効果を短時間で得る。
利点:装置は小型軽量、表面処理に有効。消費電力が比較的小さい。
欠点:影の部分は効果がない(線視性)・深部無効・一部食品で光化学的劣化が生じる。
月面での適用提案:包装表面、器具、空気滅菌(UVエア清浄)向けに有用。
------------------
6) 化学的殺菌(オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素等)
原理:酸化剤で微生物を不活化。
利点:比較的装置が簡単・軽量。広域殺菌。
欠点:残留・腐食・取扱い(特に閉鎖空間)で注意が必要。オゾンは二次空気管理が必要。
月面での適用提案:表面滅菌や機器洗浄に限定して慎重に用いる(居住区への残留を避けることが必須)。
------------------
技術の総合評価(「月面で使いやすさ」観点)
技術 微生物効果 栄養保持 装置質量/搬送負担 エネルギー負荷 運用/安全難易度 月面適合性(総合)
HPP ◎ ◎ ×(重い) 中〜高 高(高圧安全) 限定的(小型化が鍵).
放射線(e-beam) ◎ 〇 〇(e-beamは比較的コンパクト) 高 高(遮蔽・規制) 可能だが安全対策が重大.
PEF ◎(液体) ◎ 〇(小型化可) 中 中(高電圧) 液体系に非常に有効.
コールドプラズマ 〇(表面) ◎ ◎(軽い) 低〜中 低〜中 表面処理で高適合.
UV-C/PL 〇(表面) 〇 ◎ 低 低 表面・空気処理に有効
化学(オゾン等) 〇 △ ◎ 低 中(残留管理) 補助的
(出典:上掲レビュー群を総合。 )
------------------
月面での**実用的な推奨戦略(ハードル技術)**と代表プロトコル例
最終的な推奨は用途別・素材別に分けるのが合理的です:
A. 「生鮮(葉物・果菜・収穫直後)」の保存ルート(目標:表面汚染除去 → 長期保存)
1. 収穫 → 水洗(再利用水は循環処理) → コールドプラズマ表面照射(30–180 s、装置依存)で表面菌・農薬分解 → 適宜PEF(ピュレ化)かフリーズドライへ移行 → 包装(抗菌コーティングフィルム) → 保存。
理由:コールドプラズマは低温で可搬性高く、表面除染が効率的。内部はFDで長期保存。
B. 「液体系(ジュース、スープ、ピュレ)」の保存ルート(目標:液体の非熱殺菌)
1. 原料整備 → PEF処理(20–50 kV/cm、特定エネルギー 50–300 kJ/kg)で微生物不活化 → 冷却→ 小容量フリーズドライ or asepticパウチング。
理由:PEFは液体系に優れ栄養保持に優れる。装置は比較的コンパクト。
C. 「高リスク肉・タンパク系(生肉等)」の保存ルート(目標:確実な殺菌)
選択肢A:HPP(400–600 MPa, 数分) → 密封パックのまま殺菌 → 冷却・包装・保存(有効だが装置重量が課題)。
選択肢B(現実的):**E-beam照射(2–5 kGy)**で微生物レベルを飛躍的に下げる → 冷却 → FDまたは冷凍保存。
理由:肉類はHPPか照射で高信頼の殺菌が可能だが、HPPは重量的課題、照射は放射線安全の課題。
D. 「器具・包装・空気」:定期無菌化
・包装内面と出荷前表面→ UV-C or コールドプラズマ。
・空気中微生物→ HEPA+UV-C/プラズマ空気清浄。
------------------
実装上の重要留意点(安全・規制・品質)
1.「放射線(照射)」を採用する場合は Codex、各国規制、ラベル表示、
乗組員への放射線被曝回避の規定など法規面・安全面の対策が必須。Codex上の吸収線量指針(用途別)に従う。
2. HPPは圧容器安全:急激な圧力変化やシール損傷が致命的。設計・検査体制が必要。
3. 残留・酸化:プラズマや照射は酸化プロセスを促すことがあるため、抗酸化措置(天然抗酸化剤の先行処理)や真空包装併用を検討。
4. 微生物検証:各処理ごとに 3-log, 5-log の不活化レベルを標準化し、HACCPライクな工程管理プロトコルを確立。NASAの微生物安全白書など参照のこと。
------------------
試験・実証ロードマップ(研究計画案:論文・ITS実験用)
1. ラボ試験(地上)
:各技術(PEF, HPP, e-beam, cold plasma, UV)を代表食品で比較(微生物不活化、栄養・官能評価、エネルギー消費)。
2. 低g試験(パラボリック)
:プラズマや照射の挙動、昇華後の再水和に伴う周期的挙動を評価。
3. 小型実機デモ(ISSまたはラボ環境模擬)
:e-beamミニデモ、PEF小型ユニット、コールドプラズマ閉環検証。NASA系の微生物安全研究と連携推奨。
4. 月面技術実証
:小容積ユニットでの連続運用試験(食品サイクルを含む)→ 長期保存試験(組成・官能・微生物モニタリング)。
------------------
結論(推奨順・総合判断)
即時に着手すべき技術:
1. コールドプラズマ(表面滅菌) — 軽量・低メンテで導入効果が大きい。
2. PEF(液体) — 液体系食品で高い価値。
3. e-beam 照射(高リスク食材) — 放射性物質を伴わないため選択肢として有望だが遮蔽と運用規制に対応要。
長期的検討
:HPPは品質面で非常に魅力的だが「重量・建設コスト」が課題。将来の在地資材利用(ISRU)で圧力容器を現地構築できるなら導入の価値が高い。
最終設計は「用途別ハイブリッド」が最も現実的
:生鮮→プラズマ表面滅菌→(液化)PEF→FD保管、肉類はe-beam(またはHPP)→冷却/FD、等。
------------------
参考(抜粋、重要文献/報告)
:Koutsoumanis, K. et al., The efficacy and safety of high-pressure processing of food (review).
:Ghoshal, G. et al., Comprehensive review on pulsed electric field in food (2023).
:Reviews on cold plasma in food (2024–2025).
:Meat irradiation reviews & Codex dose guidance.
:NASA whitepaper: Microbial food safety in space production systems (2021).
------------------
次のステップとして下記の具体的な資料のたたき台を
作っても良いかもしれない。
また今日の内容を整理して追求していく部分があれば
追求していきたいと思います。
1. 具体的な月面用プロトコル(例:葉物→プラズマ30s→PEF→FD)を定量パラメータ(kV/cm, s, kGy等)まで落とし込む実験設計書を作る、
2. 設備設計案(PEFユニットor小型e-beam or コールドプラズマ) の概略図+質量 & 電力見積を作る、
3. **上記各法を組み合わせたHACCP的運用マニュアル(チェックリスト+検査項目)**を作る。
---------
ということ事で今回はここまで。
------------
#公邸料理人 #在外公館料理人 #伊藤のヨタばなし
#宇宙調理 #宇宙食 #universe #JAXA
#NASA #航空宇宙学会
#テクノロジー #technology
#料理 #食思弁進化 #aRim #アリム
#調理理論 #cuisine #JSASS
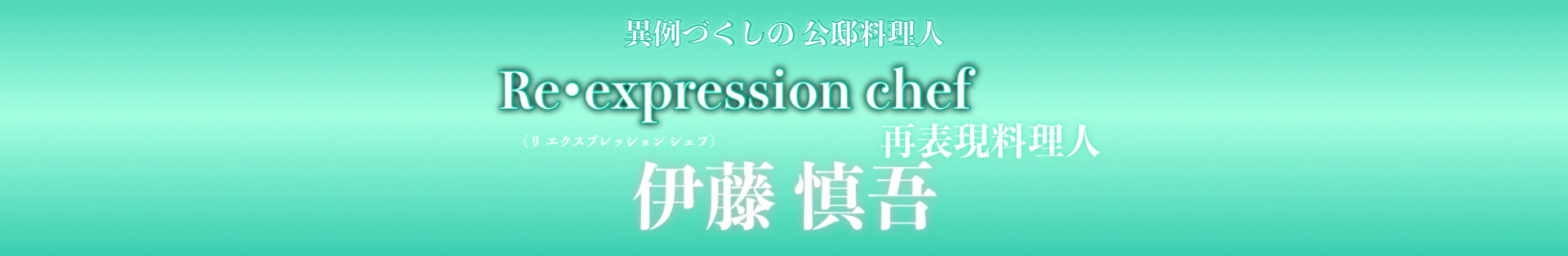
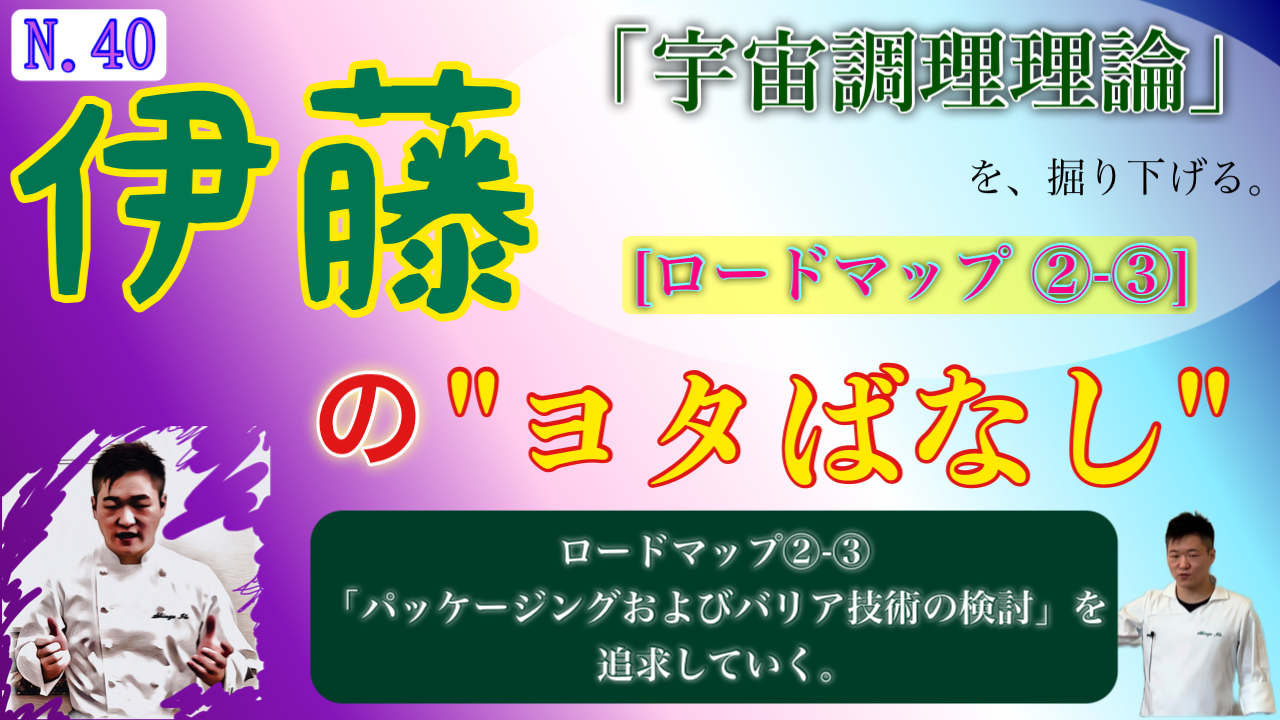


コメント