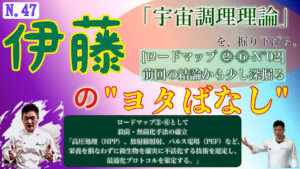
ロードマップを一つずつ。ser.
------------
「②-⑥殺菌・無菌化手法の確立」
------
それでは、同じく新章のロードマップ
「2. 食品の保存技術の確立:
– 長期保存可能で軽量・コンパクトな食品の開発や保存技術の研究を行う。」から
ロードマップ②-⑥として
殺菌・無菌化手法の確立
「高圧処理(HPP)、放射線照射、パルス電場(PEF)など、栄養を損なわずに微生物を確実に不活化する技術を選定し、最適化プロトコルを策定する。」
の続きから。
下記の前回の結論から
-------
結論(推奨順・総合判断)
「即時に着手すべき技術」から
---
[3. e-beam 照射(高リスク食材) — 放射性物質を伴わないため選択肢として有望だが遮蔽と運用規制に対応要。 ]
について、遮蔽と運用規制の課題解決には
今後どのようなアイデアとアプローチが必要ですか?
-----
「長期的検討」から
[:HPPは品質面で非常に魅力的だが「重量・建設コスト」が課題。将来の在地資材利用(ISRU)で圧力容器を現地構築できるなら導入の価値が高い。 ]
について
:「重量・建設コスト」の解決にはどのようなアプローチと現実的な課題解決のアイデアがあるか?
:在地資材利用(ISRU)で圧力容器を現地構築するならどの様な材料が現地で必要で、どの様な技術が必要であり、どの様な課題解決のストーリーが考えられますか?
---
「最終設計は「用途別ハイブリッド」が最も現実的
:生鮮→プラズマ表面滅菌→(液化)PEF→FD保管、肉類はe-beam(またはHPP)→冷却/FD、等。」
とあるが、そもそも収穫した食材の”生鮮保存”は、
可能であるか?どうか?
について、深掘っていく。
------------------
前回の結論(e-beam の有望性、HPP の重量課題、用途別ハイブリッド戦略)を踏まえて、
(A) e-beam の遮蔽/運用規制の課題解決策
(B) HPP の「重量・建設コスト」課題と
ISRU による圧力容器構築案(材料・技術・実行ストーリー)
(C) 収穫した生鮮作物の「生鮮保存は可能か?」 を、
現実的かつ論文化できるレベルで整理します。
要点ごとに実用的なアプローチと
段階的ロードマップを示し、
重要ポイントに文献参照を付けます。
⸻
A. e-beam 照射:遮蔽と運用規制の課題解決(実用方針)
要点(背景)
:電子線(e-beam)は食材の微生物不活化に有効で、放射性同位体を持たない点が 月面導入の魅力。一方で電子線加速器は「電子 → ブレムストラールング(X線)生成」を生じ、X線の遮蔽や運用上の安全規制・認可が必要です(IAEA 等の指針あり)。
技術的・運用的解決アイデア(ステップ)
1. 加速器エネルギーを制御して誘起核反応を避ける
:IAEA 等では食品照射用の機械性放射線は「E-beam ≤ 10 MeV」や「X 線 ≤ 7.5 MeV」などの上限指針があり、高エネルギーで物質が活性化(誘起放射能)するリスクを低減できる。まずは10 MeV 以下の設定を基本に運用する方針を採る。
-------
2. 専用の遮蔽モジュール設計(場所・構造でリスクを減らす)
建屋配置・遮蔽両面で対応:
①独立モジュール化(居住域から距離を取る、別棟または被覆埋設)。
②地表・レゴリスを用いた遮蔽(モジュールを部分的に埋める、レゴリスバームを積む):月レゴリスは放射線遮蔽材として実用的で、重量を地上から持ち上げる必要がない。
③薄い高Z材(鉛/タングステン)+ 厚いレゴリス層のハイブリッド遮蔽:ブレムストラールングの線源特性に合わせ局所に高Z層を用いる。
-------
3. 遠隔・自動化運用と厳格なインターロック
①加速器の「投射・停止・扉」については物理インターロックと複数レベルのソフトウェア保護を設け、人的立ち入りはリモート運転が原則。投射中は遠隔監視・自動ドアロック、積算線量のリアルタイム計測を実装。運用は地上の放射線安全手順を準用。
-------
4. リアルタイム線量測定と環境モニタ
①室外・室内の線量監視、個人線量計、作業ログを常時記録して「安全ケース(Safety Case)」を構築する。設計段階で「最悪事故シナリオ」を想定したリスク評価を行う(FA/RA:fault analysis / risk assessment)
-------
5. 法的・規制対応
①食品照射に関する国際基準(Codex、IAEA TECDOC 等)に合わせる。月面という新たな場でも、ICAO/IAEA などの国際勧告に沿った安全ケースを作成し、地上の実行主体(NASA/JAXA 等)を通じて国際合意と運用ルールを整理する必要がある(国家レベルの“放射線規制当局”と同等の安全審査プロセスを相当化)。
---
実行ロードマップ(段階的)
1. デスクトップ安全設計(安全ケース)作成:エネルギー上限、遮蔽厚、運転シーケンス、緊急停止、放射線監視。
2. 地上実証(プロトタイプ):同等遮蔽を模した構造で e-beam 食品処理を行い、放射線漏えいや残留(誘起活性化)がないことを確認(10 MeV 以下での測定)。
3. ISS 等での小規模デモ(放射線安全管理下):運用手順を精錬。
4. 月面デプロイ(段階導入):まずは埋設/レゴリス被覆型シェルに収めた小型 e-beam を運用し、実地評価。
--------------
B. HPP の「重量・建設コスト」問題と ISRU(在地資材利用)による圧力容器構築案
要点(背景)
:HPP(400–600 MPa)は食品品質保持に優れるが、等方圧力容器は高強度で厚い金属構造が必要→地球から大量輸送するとコスト高。
ーーー
アプローチの原理(軽くする/地上輸送を減らす)
1. 輸送質量を減らす分割・モジュール化設計
:圧力容器を「薄肉の金属ライナー(引張負荷を受ける)」+「外部支持構造(圧縮荷重を受ける)」に分離。薄い金属ライナー(アルミ/チタン合金のセグメント)を地球から輸送し、外部支持材を月面で作るという考え。外部支持をレゴリスベースで賄えば輸送質量は大幅に低減できる(=ISRU の基本概念)。
2. レゴリスを用いた圧縮支持シェル(外殻)
:レゴリスを溶融・焼結・硫黄バインダーで整形(例:硫黄ベースのレゴリスコンクリート、溶融ガラス/再結晶化、サイニング)して、外殻(圧縮支持体)を形成。外殻は圧力容器の外向きの張力を受けないため、圧縮強度に優れれば十分。硫黄凝固は既存研究で可能性が示されている(硫黄は低温で加工できる利点)。
3. 内部は薄肉メタルライナーまたは高強度ポリマー膜
:内側のガス保持・気密は薄い金属または高性能ポリマーライナーが担う(これは比較的軽い)。ライナーの継手は溶接/機械接合で気密化。外部のレゴリス殻が容器の外圧を抑えることで、ライナーにかかる膜応力を低減する設計。
4. 製造技術:ロボット3Dプリント + 太陽熱/ミラー加熱 / 電気加熱のコンビ
:レゴリスの成形は3D プリンティング(押出し)/レーザー/太陽集中加熱で焼結または溶融する実験が進んでいる(NASA・研究機関で実証段階)。冷間焼結(cold sintering)など低温プロセスも検討材料。
ーーー
必要な在地材料と技術
材料:月レゴリス(主要)、硫黄(レゴリスに含まれる硫黄が使えるかは地質依存だが、硫黄は外来搬入も想定)、アルカリ溶剤やバインダー(現地採取が難しければ最小限輸送)。
技術:レゴリス採取・分級、3D 押出成形、ソーラー集中溶融(またはレーザー焼結)、内部金属ライナーの取付・溶接(自動ロボット)、気密試験(漏洩検査装置)。
---
課題と対策
1. 気密性の確保:レゴリス外殻は圧縮体に優れるが、気密は内部ライナーに依存。ライナーの継手・シール技術(溶接品質)を自動化する必要。→対策:金属ライナーは地上で加工精度高く製作し、月面でモジュール結合する方法。
2. 熱・温度サイクル:昼夜で温度差が大きく、熱膨張差がシールを損なう恐れ。→対策:膨張差を吸収するジョイント設計や、内外の断熱(PCM・エアロゲル)を実装。
3. 耐久性(疲労・微小亀裂):レゴリス構造は脆性で疲労に弱い。→対策:繊維補強(溶融レゴリス由来の繊維)や複合化を検討。
-------
実行ストーリー(段階的)
1. 選地と資源査定:氷・硫黄等の局在調査、レゴリス組成調査。
2. 地上の材料試験:月模擬レゴリスでの硫黄コンクリート・冷間焼結の圧縮試験、気密化ライナーの接合実験。
3. ロボット製造実証:小規模の外殻(数 m)を自動プリントし、地上での気密・耐圧試験。
4. 月面パイロット:小径の HPP 支持シェルを現地製造し、内部に輸送済みの金属ライナーを装着、低圧での試験 → 段階的に設計値へ拡大。
-------
C. 「収穫した食材の生鮮保存は可能か?」(可否+実務的対策)
結論(簡潔)
可能だが制約付き:月面での「生鮮(葉物・果菜)の栽培と即時消費」は実用的かつ精神的メリットが大きい(ISS Veggie 等の成功例)。長期保存(何ヶ月も)を期待するなら、冷蔵+MAP/可食コーティング/滅菌処理(表面)を組み合わせる等の対策が必須で、最終的には加工(FD など)して長期保管するのが現実的。
理由と実務的手順
1. ISS の実績:ISS の Veggie 等でレタスやトマト等の栽培・収穫が可能で、乗組員が直接食べている(短期間消費)。ただし ISS でも保存は数日〜数週間単位が一般的。
ーーー
2. 月面特有の課題:乾燥空気、循環系に混入する微粒子、微生物制御、水の消費、温湿度管理。これらは生鮮保存の劣化を早める。
ーーー
3. 延命処置(現実策):
冷蔵(低温保存)
:地上と同様に効果大。ただしエネルギーが必要。夜間に電力が有限なら難しい。
MAP(Modified Atmosphere Packaging)
:袋内の O₂/CO₂ を調整して呼吸速度を下げる(数日→数週間延長)。複合的に用いると有効。
Edible coatings(例:キトサン)
:抗菌・水分損失防止の効果があり、宇宙環境でも実用性高い(軽量で化学残留懸念が低い)。研究では果菜の保鮮で有効。
表面滅菌(コールドプラズマ / UV)
:収穫直後の表面菌低下に有効で、長期化の底上げに寄与。
ーーー
4. 現実的運用モデル:
即食ゾーン
:収穫→前処理(洗浄)→表面滅菌(低温プラズマ)→即消費または短期冷蔵(数日)。
延命販売流通(基地内ストック)
:収穫→洗浄→エディブルコーティング(キトサン)→MAP→冷蔵で数週間。
長期保存
:収穫→加工(ピュレ化→PEF または加熱殺菌)→フリーズドライ(FD)→軽量パウチで保管。
--------------
まとめ(実務的勧告)
短期→中期(数日〜数週間)の生鮮保存は
「冷蔵 + MAP + 食用コーティング + 表面滅菌」で
現実的に達成可能(ただし電力・水の制約下で最適化が必要)。
「長期保存(数ヶ月〜年)」は「加工(FD 等)して保存」するのが現実的。
野菜を丸ごと長期保存する技術は現時点ではコスト比で非効率。
--------------
最終的な実装提案(短期→中期→長期ロードマップ)
1. 短期(1–3年)
:小型 e-beam(≤10 MeV)地上プロトタイプと
安全ケース作成。コールドプラズマ装置を
栽培モジュールに導入して表面処理を実証。
生鮮保管は MAP + キトサンコーティングの地上試験。
2. 中期(3–7年)
:ISS やラボで PEF(液体処理)や e-beam の
小型デモ運用。HPP は「小ロット」機で試験。
ISRU 建設技術(レゴリス焼結・硫黄コンクリート)の地上・月模擬実験を進める。
3. 長期(7–15年)
:月面でのレゴリス外殻を用いた HPP 実験施設(段階的に規模拡大)、
e-beam 常設モジュール運用、
食品生産→加工→FD の循環系を確立。
--------------
参考(抜粋)
:IAEA, Manual of Good Practice in Food Irradiation (TECDOC/TRS 等)。e-beam/X線のエネルギー上限等。
:e-beam 入門・比較記事(技術特徴、遮蔽や運用面の概説)。
:HPP のレビュー(微生物不活化、機器の課題)。
:レゴリス建設/硫黄・3D プリント研究(ISRU に関する近年の研究)。
:ISS の植物栽培実績(Veggie 等)と生鮮の現状。
:キトサン/MAP による鮮度保持のレビュー論文。
---------
ということ事で今回はここまで。
------------
#公邸料理人 #在外公館料理人 #伊藤のヨタばなし
#宇宙調理 #宇宙食 #universe #JAXA
#NASA #航空宇宙学会
#テクノロジー #technology
#料理 #食思弁進化 #aRim #アリム
#調理理論 #cuisine #JSASS
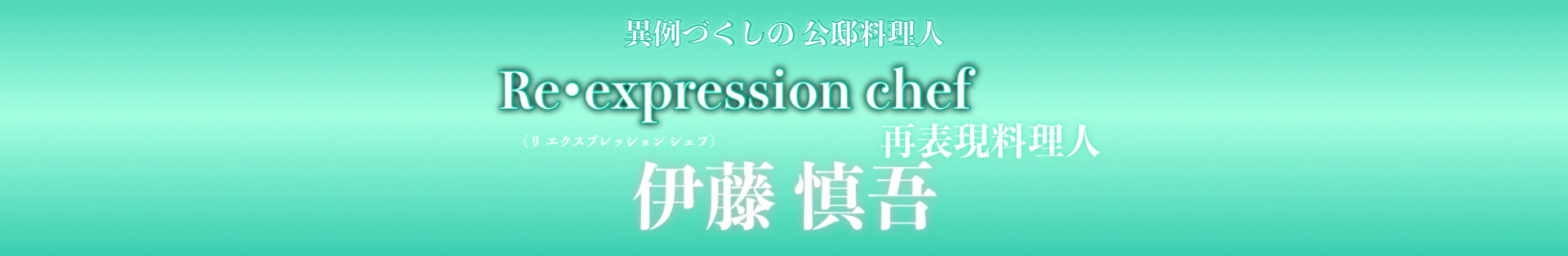
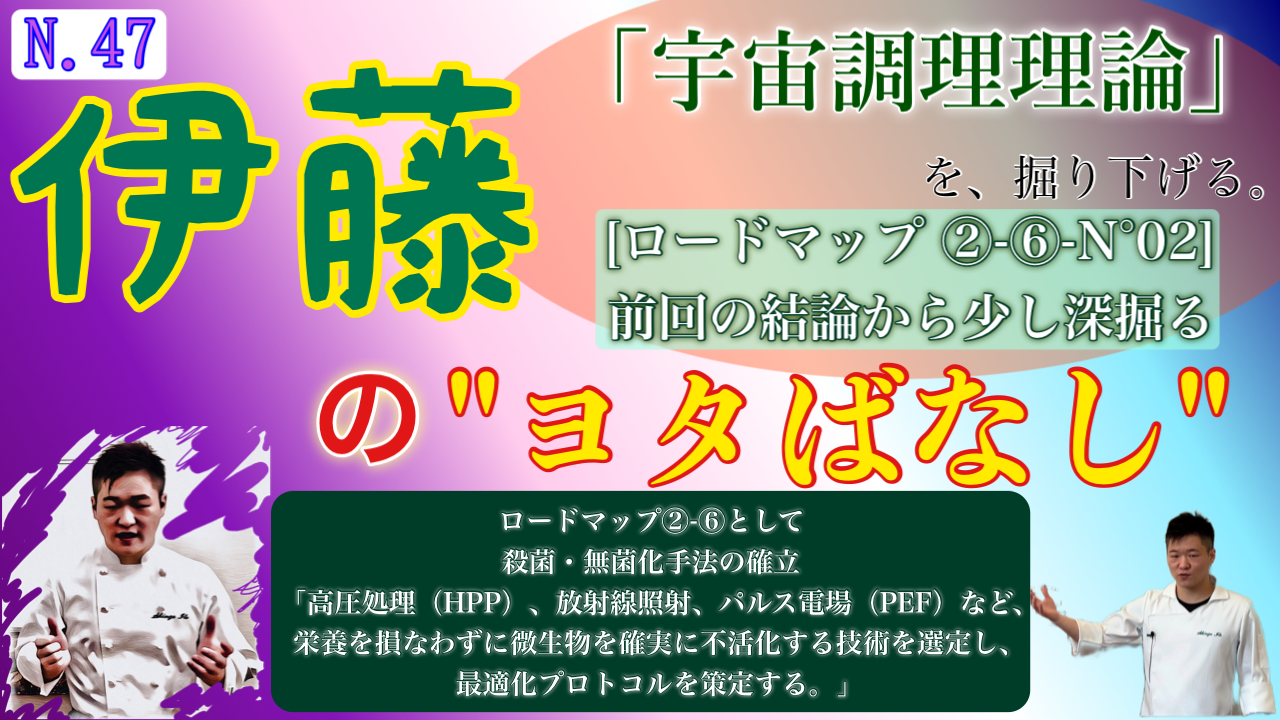


コメント