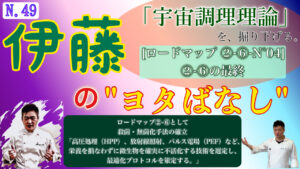
HP N°84. [伊藤のヨタばなし] 宇宙調理に関して:宇宙調理理論
ロードマップ②-⑥-N°04ついて。
ロードマップを一つずつ。ser.
------------
「②-⑥殺菌・無菌化手法の確立」
------------
前回の続きから。
ロードマップ②-⑥の最終。
以下は議論用ドラフト(短期で使える要点版)です。
各項目とも「次に何をするか」が分かるようにして。
----------------
① e-beam 安全ケース(要約版)
目的(要旨)
食品殺菌/保存処理として電子線(e-beam)を
月面モジュールに導入する際の安全設計と運用要件の要約。
基本仕様(設計前提)
加速器エネルギー(推奨)
:≤ 10 MeV(誘起放射能リスク低減のため)
運用モード
:ロボット搬送での密閉照射バッチ(パッケージ単位)
想定バッチサイズ
:小〜中ロット(例:1–10 kg/バッチ、初期)※運用に応じ調整
--------------
遮蔽・配置概念
配置:居住区から距離を取った別棟・外縁部に設置。
可能なら部分埋設(掘削してモジュールを下げる)し、
上面をレゴリスで被覆する。
遮蔽方針:レゴリス外被覆(数十〜80 cm 程度、局所評価必要)
+局所高Zライナー(必要最小限:薄い高密度材)によるハイブリッド遮蔽に。
搬送経路:自動化した密閉搬送チェンネル(人は照射直近に入らない運用)を使用。
-------
運用安全要件
:遠隔運転と完全インターロック(二重物理ロック+ソフトウェアロック)。
:リアルタイム線量モニタ(室内・外周・人員用)、個人線量計運用。
:緊急停止(E-STOP)と安全遮断フロー、定期保守と校正。
:運用者資格(放射線安全責任者)、定期訓練・ドリル。
-------
測定・検証(必須)
:遮蔽性能の実測(照射前に模擬線量測定)。
:計測ログの保存(線量履歴・開閉履歴)。
:初期運用で段階的に照射線量と
官能/微生物評価を行う(バッチ評価フェーズ)。
規制・参照基準(準備項目)
:国際的基準の参照(Codex / IAEA の食品照射指針相当を準備)
:運用許認可に必要な書類・安全ケース(Safety Case)作成の予定(地上の放射線安全手順を参照)。
-------
短期アクション(1–2 週間で)
1. 遮蔽概念図(平面+断面)作成(レゴリス厚の初期見積)
2. インターロック/遠隔運転のフローチャート作成
3. 外部照射ラボと連携して「同規模・エネルギーでの地上デモ計画」を立案
--------------
② HPP-ISRU 概念仕様シート(要約版)
目的(要旨)
HPP(高圧処理:例 400–600 MPa)を
月面で実現するために、
地上輸送最小化+在地資材(レゴリス)で
外殻を作るハイブリッド構成を提案。
-------
基本方針(設計前提)
処理圧力レンジ(目標)
:400–600 MPa(用途により調整)
設計コンセプト
:薄肉気密ライナー(地上輸送) + レゴリス製 外殻(現地製造)
内ライナー
:気密・耐食金属(例:Ti合金、ステンレス、または高性能ポリマー複合)モジュール(地上加工)
外殻
:レゴリス+バインダー/焼結で圧縮支持体を現地形成(硫黄コンクリート、焼結レゴリス、レーザー焼結 等)
-------
主要製造ステップ(フローチャート)
1. 現地資源評価(レゴリス組成・含水/硫黄の有無)
2. レゴリス採取・分級・粉砕
3. 外殻形成:選択
(A)硫黄結合混練押出
(B)レーザー・太陽熱焼結
(C)冷間結合+繊維補強
4. 外殻硬化/調整
→ 内ライナー据付(ロボットによる位置決め・締結)
5. 気密試験・低圧試験
→ 段階的耐圧試験で設計圧に到達
-------
主要リスクと緩和策
気密性リスク:内ライナーの継手が鍵。
→ 地上で高精度に製作、月で機械的フランジ+溶接/シールで接合、ヘリウムリークテスト(または代替)で検証。
熱サイクル脆化:昼夜温度差で材料劣化。
→ 断熱(エアロゲル/PCM)、膨張吸収ジョイント設計。
外殻強度/脆性:レゴリス材料の均一化と繊維補強が鍵。
→ 地上模擬試験でレシピ確定。
製造自動化:人手依存を低減。
→ ロボット3Dプリント + 自動品質検査(視覚+超音波)を導入。
-------
概算物資フロー(概念)
地上搬送:内ライナーモジュール(複数)、機械(ロボット・組立治具)、少量高Z遮蔽材など
現地調達:レゴリス(主要)、可能ならバインダー(硫黄等)または焼結プロセスでバインダー不要を目指す
-------
短期アクション(2–4 週間で)
1. 内ライナーの寸法・材質候補と概算重量リスト作成
2. レゴリス外殻候補手法の評価(硫黄合成 vs 焼結 vs 繊維複合)— 地上模擬試験計画策定
3. ロボット組立工程の工程図(自動化ポイント)作成
--------------
③ プロトタイプ試験仕様書(ドラフト:1–2 週間で最終化可能)
目的
上の安全・設計前提に基づき、初期プロトタイプ食品を製造し、加速老化試験で保存性と官能品質の変化を評価する。
対象食品(例)
A. 葉物(例:レタス) — 生鮮延命試験
B. トマトピュレ(液状) — PEF + FD 試験(液体処理)
C. タンパク基材(例:培養肉代替 or 鶏代替) — HPP / e-beam 処理候補
-------
処理プロセス(試験セット)
1. 表面処理
:コールドプラズマ(30–120 s)→ エディブルコーティング(キトサン)→ MAP(O₂ 低下/CO₂ 増)
2. 液体処理
:PEF(例 15–25 kV/cm、適正エネルギー)→ FD(フリーズドライ)
3. 高度殺菌候補(条件は安全ケース確定後)
:e-beam(≤10 MeV、線量範囲 0.5–5 kGy 試験)または HPP(段階的 100→400 MPa)
-------
加速老化条件
温度ストレス:40°C(加速)/60°C(強加速)、
測定期間例:0, 1, 2, 4, 8 週(短期)→ 長期は 3–12 ヶ月
放射線ストレス(オプション、e-beam ガンマ外注):低線量酸化ストレス(例 0.1–1 kGy)を追加で評価(安全確定後)
湿度条件:封入(低RH)/非封入(高RH モデル)を並列評価
-------
評価指標
微生物:総菌数、真菌、指標菌(E. coli / Salmonella)
物理化学:水分活性(aw)、色 (Lab ΔE)、テクスチャ(TPA 指標)、過酸化物価(PV)、揮発性風味(GC)
栄養:ビタミンC、主要アミノ酸の保持率(必要に応じ測定)
官能:パネル評価(5–10 名のトレーニングパネル)による味・香り・食感スコア
包材評価:WVTR、OTR(包装材性能)
-------
サンプル数(例)
各処理 × 各条件 × 3 バッチ(各バッチで n=3 の複製)
=最初は小スケールで 50–100 サンプル程度を推奨
-------
タイムライン(概略)
Week 0–2:試験仕様確定、外注(PEF/e-beam/HPP候補ラボ)への打診
Week 2–6:プロトタイプ製造(表面処理、PEF、FD 等)と短期保存試験開始(40°C)
Week 6–12:中間評価、条件調整、e-beam/HPP の安全確保後の高リスク試験移行
-------
安全前提
e-beam / HPP を用いる試験は安全ケース/設計の承認後に実施(地上外注で代替可能な試験は先行して行う)
--------------
---------
ということ事で今回はここまで。
------------
#公邸料理人 #在外公館料理人 #伊藤のヨタばなし
#宇宙調理 #宇宙食 #universe #JAXA
#NASA #航空宇宙学会
#テクノロジー #technology
#料理 #食思弁進化 #aRim #アリム
#調理理論 #cuisine
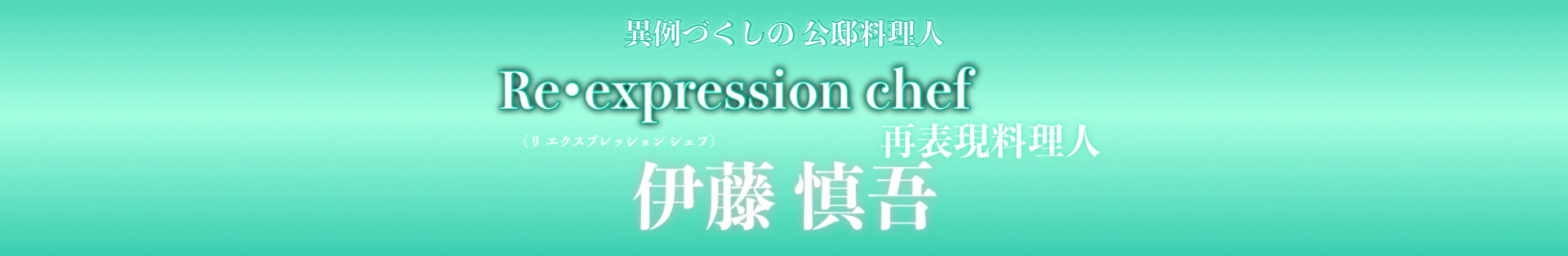
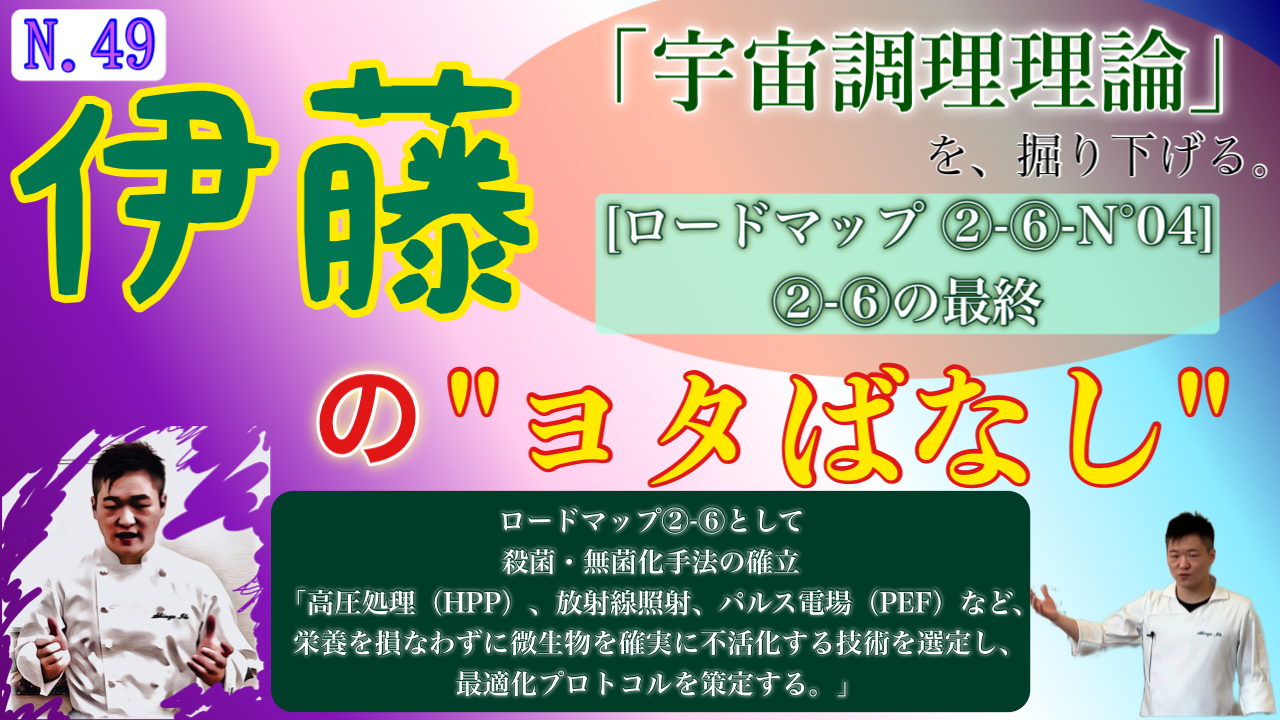


コメント